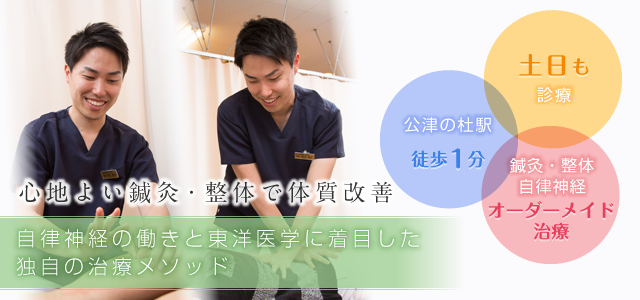

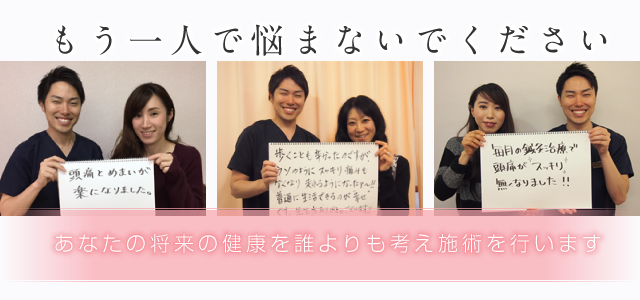


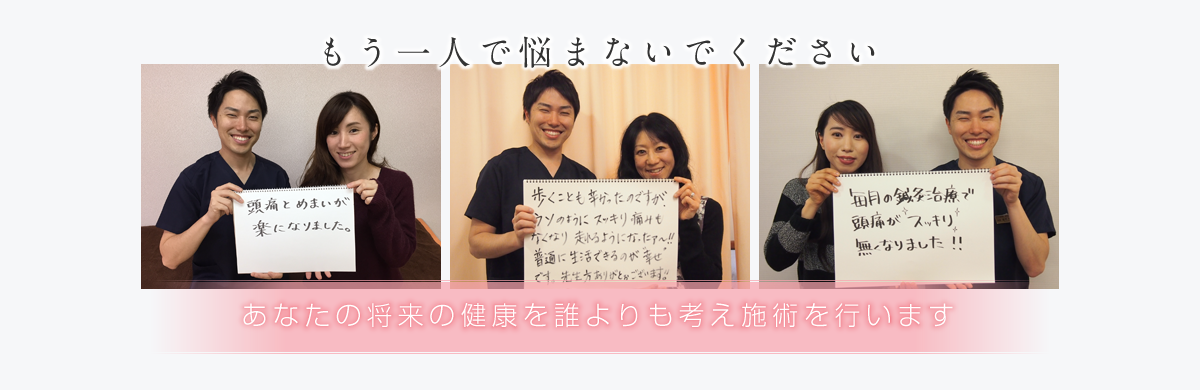
- Blog記事一覧 -春に乱れやすい「肝」による不調とケア
春は東洋医学において「肝」の季節とされています。
肝は血の巡りを調整し気(エネルギー)の流れをスムーズにする重要な働きを担っています。
しかしストレスや生活習慣の乱れによって肝の働きが低下すると、さまざまな不調が現れることがあります。
今回は肝の役割や不調のサイン、そして鍼灸によるケアについてご紹介します。
東洋医学における肝の主な役割は以下の3つです。
1. 気の流れ(気機)を調整する
肝は気の流れをスムーズにする働きがあり全身の機能を調整します。この働きが滞るとイライラや不安感、ため息が増えるなどの精神的な不調が現れます。
2. 血を貯蔵し必要な場所へ供給する
肝は血液を貯蔵し必要に応じて全身に送り出します。特に目や筋肉に深く関わっており肝の血が不足すると目の疲れやかすみ目、筋肉のこわばりやこむら返りが起こりやすくなります。
3. 自律神経のバランスを整える
肝はストレスと密接に関係しておりストレスが過剰になると自律神経のバランスが乱れ、不眠や胃腸の不調が引き起こされます。
肝の働きが低下すると以下のような症状が現れることがあります。
精神的な不調:イライラしやすい、怒りっぽい、不安感、憂鬱感
目の不調:目の疲れ、乾燥、かすみ目、充血
筋肉や関節の不調:こむら返り、肩こり、関節の痛み
消化器系の不調:食欲不振、胃のもたれ、下痢や便秘の繰り返し
自律神経の乱れ:寝つきが悪い、眠りが浅い、寝ても疲れが取れない
特に春は気温の変化が激しく自律神経が乱れやすいため、肝の不調を感じる人が増えやすい時期です。
鍼灸では肝の働きを整え気や血の巡りを改善することで、上記の症状を緩和することができます。主に以下のような施術を行います。
1. 「太衝(たいしょう)」への鍼刺激
太衝は足の甲にあるツボで肝の気の流れをスムーズにする効果があります。ストレスによるイライラや自律神経の乱れを整えるのに有効です。
2. 「肝兪(かんゆ)」への施術
肝兪は背中にあるツボで肝の働きを強化し血の巡りを改善します。眼精疲労や筋肉のこわばりがある方におすすめです。
3. お灸で温める「三陰交(さんいんこう)」
三陰交は内くるぶしの上にあるツボで血の巡りを良くし肝・脾・腎を調整する働きがあります。女性の月経トラブルや冷え性の方にも効果的です。
また生活習慣の改善も大切です。適度な運動や深呼吸を心がけリラックスできる時間を作ることが、肝の負担を減らすポイントとなります。
肝は身体と心のバランスを整える重要な臓器です。
ストレスや生活習慣の影響を受けやすく、不調が続くとさまざまな症状を引き起こします。
鍼灸施術では、肝の機能を高め、気や血の巡りを改善することで、不調を和らげることができます。
春は肝の不調が出やすい時期ですが鍼灸によるケアと日々のセルフケアを取り入れることで、心身ともに健やかに過ごせるようになります。
ぜひ鍼灸を活用して肝を整え元気な毎日を送りましょう。
お問い合わせは気軽にLINEから!
セドナ整骨院・鍼灸院公津の杜院
千葉県成田市公津の杜2-14-1セキードセキ1F
鍼灸師 伊藤