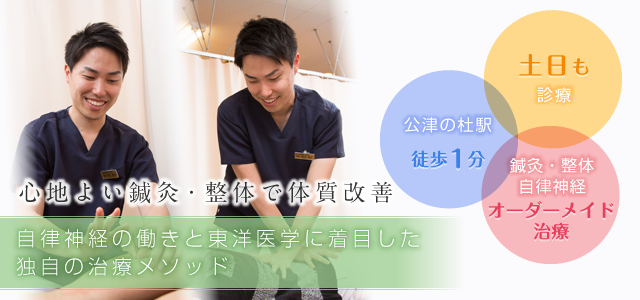

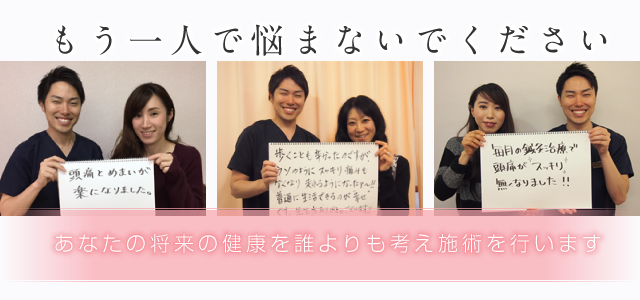


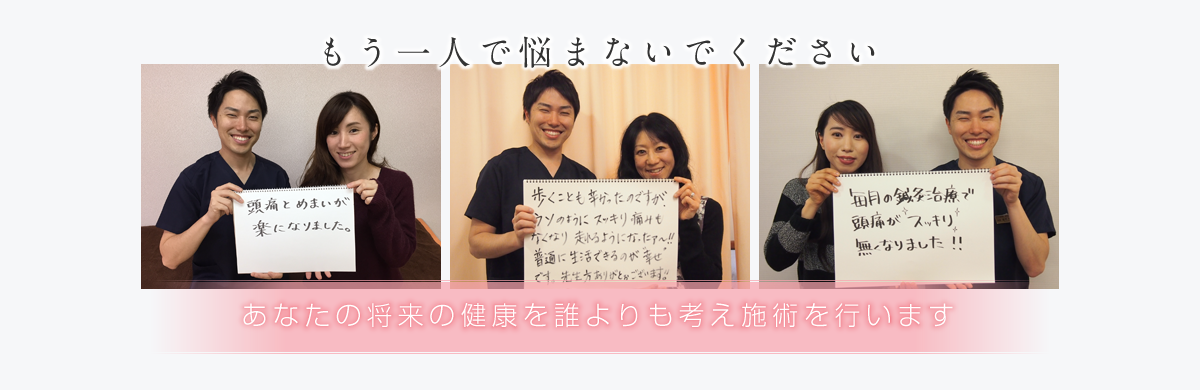
- Blog記事一覧 -2月, 2025 | セドナ整骨院・鍼灸院・カイロプラクティック 公津の杜院の記事一覧
2月, 2025 | セドナ整骨院・鍼灸院・カイロプラクティック 公津の杜院の記事一覧
春になると多くの人が悩まされる花粉症。
くしゃみや鼻水、目のかゆみなどの症状がつらいですよね。花粉症の症状を軽減するためには薬だけでなく、体のケアを取り入れることも大切です。
今回は花粉症の症状を和らげるための体のケア方法についてご紹介します。
花粉症の症状が出る大きな原因の一つに、「免疫バランスの乱れ」があります。特に血流やリンパの流れが悪くなると、体が過剰に反応しやすくなります。
そのため血流を改善するケアが有効です。
・首や肩のコリをほぐす
首や肩がこっていると鼻の粘膜の血流が悪くなり、症状が悪化しやすくなります。軽いストレッチやマッサージを取り入れ筋肉の緊張を和らげましょう。
・入浴で血行促進
ぬるめのお湯(38~40℃)にゆっくり浸かることで血流が改善し、副交感神経が優位になります。これにより自律神経のバランスが整い、花粉症の症状が和らぎやすくなります。
腸内環境の乱れは免疫機能に影響を与え、花粉症の症状を悪化させる原因になります。発酵食品や食物繊維を積極的に摂ることで腸内環境を整えましょう。
■おすすめの食品
・発酵食品(納豆、ヨーグルト、味噌、ぬか漬け など)
・食物繊維を多く含む食品(ゴボウ、海藻、キノコ類 など)
・抗酸化作用のある食品(緑黄色野菜、ナッツ類 など)
また白砂糖や加工食品の摂りすぎは腸内環境を乱す原因となるため、できるだけ控えるのがおすすめです。
東洋医学では花粉症は「肺」や「脾」の働きの低下、気の巡りの滞りが関係していると考えられています。鍼灸施術では体のバランスを整えながら、鼻詰まりや目のかゆみなどの症状を和らげることが可能です。
〇鍼灸で期待できる効果
・鼻粘膜の炎症を抑え鼻詰まりや鼻水を改善
・自律神経を整え免疫の過剰反応を抑える
・血流を促進し体質を改善
〇花粉症に効果的な施術部位
・迎香(げいこう)(小鼻の横)…鼻の通りを良くする
・合谷(ごうこく)(手の甲の親指と人差し指の間)…免疫調整に作用
・風池(ふうち)(首の後ろ)…目のかゆみや鼻詰まりを軽減
・足三里(あしさんり)(すねの外側)…消化機能を整え、免疫バランスをサポート
花粉症シーズンの前から鍼灸を受けることで症状が軽減しやすくなるため、早めのケアがおすすめです。
不規則な生活や睡眠不足は自律神経の乱れを引き起こし、花粉症の症状を悪化させる原因になります。
・質の良い睡眠をとる
睡眠不足は免疫機能を低下させるため十分な睡眠を確保しましょう。特に、22時~翌2時の間は成長ホルモンが分泌されるゴールデンタイムなので、この時間帯にしっかり眠ることが理想的です。
・適度な運動を取り入れる
ウォーキングや軽いストレッチなどの適度な運動は血流を良くし、免疫機能を正常に保つのに役立ちます。屋外での運動が難しい場合は室内でできるヨガやストレッチを取り入れてみましょう。
花粉症は薬だけでなく日常のケアや鍼灸施術によって症状を軽減することができます。血流を良くすること、腸内環境を整えること、鍼灸で体のバランスを整えること、そして規則正しい生活を送ることが大切です。今年の春はぜひ鍼灸を取り入れながら体のケアを行い、少しでも快適に過ごしましょう!
お問い合わせは気軽にLINEから!
セドナ整骨院・鍼灸院公津の杜院
千葉県成田市公津の杜2-14-1セキードセキ1F
鍼灸師 伊藤
風が強い日に頭痛が出ることはありませんか?
「天気が悪くなると頭が痛い」「風が強い日はなんとなく調子が悪い」と感じる方も多いのではないでしょうか。
実は風が強い日には気圧の変化や冷えなど、さまざまな要因が重なると頭痛が起こりやすくなります。
今回は風が強い日に頭痛が起こる主な原因と、効果的な対策についてご紹介します。
1. 気圧の変化
強風が吹く日は低気圧が接近していることが多く気圧が急激に変化します。気圧の変動により血管が拡張または収縮し、自律神経が乱れることで頭痛が引き起こされることがあります。特に片頭痛を持っている方は、気圧の影響を受けやすいため注意が必要です。
2. 冷えによる血流の悪化
風が強いと体温が奪われやすく特に首や肩が冷えると血流が悪くなります。これにより筋肉が緊張しやすくなり、緊張型頭痛が発生することがあります。冬場だけでなく春先や秋口など気温の変化が大きい時期も要注意です。
3. 風による花粉やホコリの影響
春先は風が強いと花粉やホコリが舞い上がり、それを吸い込むことで鼻づまりやアレルギー反応を引き起こすことがあります。鼻の奥が炎症を起こすと副鼻腔炎(ちくのう症)による頭痛が発生することも。特に花粉症の方は強風の日に外出すると症状が悪化しやすいため、マスクやゴーグルの着用をおすすめします。
4. 自律神経の乱れ
強風の日は耳から入る風の音がストレスとなり、自律神経のバランスが乱れることがあります。体が無意識に緊張したり風による気圧変動がストレスになったりすることで、片頭痛や緊張型頭痛を引き起こすことがあります。
1. 首や肩を冷やさない
マフラーやネックウォーマーを活用し首元の冷えを防ぎましょう。特に外出時は風が直接当たらないようにするのがポイントです。
2. 自律神経を整える
深呼吸やストレッチを行いリラックスを心がけましょう。また日頃から規則正しい生活を送り自律神経のバランスを整えることが大切です。
3. 花粉やホコリの対策をする
室内の湿度を適度に保ち空気清浄機を活用するのも有効です。帰宅後は衣類の花粉をしっかり払うようにしましょう。
4. 鍼灸施術を受ける
鍼灸は気・血・水の巡りを整えることで、頭痛の予防や緩和に効果的です。特に自律神経の乱れや血流の滞りが原因となる頭痛には、鍼やお灸の施術が有効です。首や肩のコリをほぐしリラックスすることで、頭痛の発生を抑えることができます。
風が強い日は気圧の変化や冷え花粉などが影響し頭痛が起こりやすくなります。首元の防寒や自律神経を整える習慣を意識し、花粉対策や鍼灸施術を取り入れることで頭痛を予防・軽減することができます。
「風が強いと頭痛がつらい」と感じる方は、ぜひ今回ご紹介した対策を試してみてください。体調の変化に気をつけながら快適に過ごしましょう!
お問い合わせは気軽にLINEから!
セドナ整骨院・鍼灸院公津の杜院
千葉県成田市公津の杜2-14-1セキードセキ1F
鍼灸師 伊藤
少しずつ暖かくなり春の訪れを感じる季節になりました。
しかしこの時期は「なんとなく体がだるい」「眠気が取れない」「頭が重い」といった不調を感じる方が増える時期でもあります。
これは気温の変化や花粉の影響、自律神経の乱れが関係していると考えられます。
今回は春に起こりやすい不調と、その対策としての鍼灸の効果についてご紹介します。
1. 寒暖差による自律神経の乱れ
春は朝晩の気温差が大きく体温調節を司る自律神経が乱れやすくなります。その結果、疲れやすさや倦怠感、頭痛などの症状が出やすくなります。
2. 花粉症による不調
花粉が飛び始めるこの時期は、鼻づまりや目のかゆみだけでなく頭痛や倦怠感を引き起こすこともあります。さらに鼻呼吸がしづらくなることで睡眠の質が低下し、疲労が抜けにくくなる方も多いです。
3. 冬の間に溜まった老廃物の影響
冬は寒さで代謝が低下し老廃物が体に溜まりやすくなります。春になると体がデトックスしようと働きますが、うまく排出できないとむくみやだるさが続いてしまいます。
春の不調を軽減するためには体の巡りを良くし、自律神経のバランスを整えることが大切です。鍼灸は以下のような効果が期待できます。
・ 自律神経の調整
鍼やお灸でツボを刺激することで緊張した身体をリラックスした状態へ導きます。これにより疲労感やだるさが軽減され質の良い睡眠をとりやすくなります。
・ 花粉症の症状緩和
「迎香(げいこう)」や「合谷(ごうこく)」といったツボを刺激すると、鼻づまりが軽減されやすくなります。また体質改善を目的とした鍼灸施術を続けることで、花粉症の症状そのものが和らぐことも期待できます。
・ 血流促進とデトックス
「足三里(あしさんり)」や「三陰交(さんいんこう)」などのツボを刺激すると、血流が促進され老廃物の排出を助けます。また当院で取り扱っている陰陽五行オイルを使い脚のオイルトリートメントを行うことでむくみや冷えの改善にもつながり体がすっきりします。
日々の生活で意識すると良いポイントもご紹介します。
・ 朝日を浴びる → 体内時計が整い自律神経のバランスが安定しやすくなります。
・ 軽い運動をする → ウォーキングやストレッチで血流を良くしましょう。
・ 食事に気をつける → 春は東洋医学の「肝」の働きが活発になる時期です。緑黄色野菜や酸味のある食べ物を取り入れると良いでしょう。
この時期の不調を放っておくと、5月病のような長引く不調につながることもあります。春の体の変化を上手に乗り切るためにも鍼灸を活用しながら体を整えていきましょう。気になる症状があればぜひご相談ください。
お問い合わせは気軽にLINEから!
セドナ整骨院・鍼灸院公津の杜院
千葉県成田市公津の杜2-14-1セキードセキ1F
鍼灸師 伊藤
こんにちは、セドナ整骨院・鍼灸院公津の杜院の伊藤です。
冬になると寒さの影響で外出の機会が減り、運動不足になりがちですよね。
「最近、体が重く感じる」「肩こりや腰痛がひどくなった」といった不調を感じる方も多いのではないでしょうか?
実はこうした症状は冬の運動不足が大きく関係しています。
今回は冬の運動不足が引き起こす身体の不調と、それに対する鍼灸やセルフケアのアプローチについてご紹介します。
冬の寒さによって体を動かす機会が減ると以下のような不調が現れやすくなります。
1. 血行不良による冷えやむくみ
運動をしないと血流が滞りやすくなり冷えやむくみが悪化します。特に足先や手先が冷たくなったり夕方になると脚がむくんだりするのは、血流の低下が原因です。
2. 筋力低下による肩こり・腰痛の悪化
運動不足が続くと筋力が衰え姿勢を支える力が弱まります。その結果肩こりや腰痛がひどくなったり、体がだるく感じたりすることが増えます。デスクワークの方は特に注意が必要です。
3. 代謝の低下による体重増加や疲れやすさ
運動量が減ると基礎代謝が落ち太りやすくなります。またエネルギーをうまく燃焼できず疲れやすくなることもあります。
4. 自律神経の乱れによる不調
適度な運動は自律神経のバランスを整える効果があります。しかし運動不足が続くと自律神経が乱れ寝つきが悪くなったり、ストレスを感じやすくなったりします。
冬の運動不足による不調を防ぐために以下のセルフケアを意識してみましょう。
1. 簡単なストレッチや軽い運動を取り入れる
寒い冬でも自宅でできる簡単なストレッチや軽い運動を取り入れることで、血行を促進し筋力低下を防ぐことができます。例えばお風呂上がりや朝起きたときに軽く体を伸ばすストレッチなどが効果的です。
2. ウォーキングを習慣にする
寒い日でも少し厚着をしてウォーキングをすることで、血流が良くなり冷えやむくみの改善につながります。無理に長時間歩く必要はなく近所を10~15分歩くだけでも良いと思います。最初はおしゃべりができるくらいの速さで歩くことがポイントです。
3. 日常生活の中で体を動かす工夫をする
エレベーターではなく階段を使う、家事をするときに意識して体を大きく動かすなど、日常の中で少しでも体を動かす意識を持つと運動不足を解消しやすくなります。
運動不足による不調を改善するにはセルフケアと合わせて鍼灸の力を活用するのもおすすめです。鍼灸には以下のような効果があり、冬の運動不足による体の不調を和らげるのに役立ちます。
1. 血流を改善し冷えやむくみを解消
鍼灸は血行を促進する効果があり特に「三陰交(さんいんこう)」「足三里(あしさんり)」といったツボを刺激することで、下半身の冷えやむくみを改善します。
2. 筋肉のこわばりを緩め肩こりや腰痛を軽減
鍼灸によって筋肉の緊張を和らげることで、肩こりや腰痛の症状が改善されます。特にデスクワークの方は「肩井(けんせい)」や「大椎(だいつい)」といったツボを刺激すると、血行が良くなりこりが軽減されます。
3. 自律神経を整え、ストレスや睡眠の質を改善
鍼灸は副交感神経を優位にし、リラックス状態を作り出す効果が期待できます。「百会(ひゃくえ)」や「神門(しんもん)」といったツボを刺激すると、ストレスが軽減し睡眠の質も向上します。
冬の運動不足はさまざまな身体の不調を引き起こします。ですが軽いストレッチやウォーキングを習慣にしたり、鍼灸を取り入れたりすることで血流や自律神経のバランスを整え健康を維持することができます。
寒い季節こそしっかりと体を整え春を元気に迎えましょう!ご不明な点があればお気軽にご相談ください。
お問い合わせは気軽にLINEから!
セドナ整骨院・鍼灸院公津の杜院
千葉県成田市公津の杜2-14-1セキードセキ1F
鍼灸師 伊藤